お茶の更なる可能性に挑む



栽培面積500ヘクタール、茶生産者は約200人、製茶工場は約40軒あります。磐田原大地に広がる茶園は 、地形が平坦で温暖な気候に恵まれているため、静岡県内でも極早場所の産地であり、4月の中旬から新茶の摘み採りが始まります。その恵まれた地形から茶園の基盤整備もされ、ヤブキタの再改植も進む一方で、 それぞれ特徴のあり新品種の導入も進んでいます。また、乗用管理機の導入が早くからされ、その普及率 は県内上位です。次世代を担う若い後継者も多く収納しており、将来が楽しみな産地でもあります。



いわた茶の特徴
渋みと旨みが調和し味わい深さがあり、さわやかですっきりとした香りと、澄んだ水色(すいしょく)が特徴のお茶です。個人経営での生産者が多く、普通煎茶から深蒸煎茶までこだわりを持って幅広く製造されているため、バラエティに富んだお茶が楽しめます。
煎茶の種類
普通煎茶
煎茶は日本で最も飲まれており、生産の80%を占めています。抽出すると澄んだ山吹色をしており、 旨みと渋みの調和がよく、すっきりとした味が特徴です。
深蒸し煎茶
通常、煎茶の時間は30秒〜40秒とされていますが、深蒸し煎茶の場合は1分以上となり、まろやかでコクが深い味わい になります。長く蒸すことで、茶葉は細かく崩れているのが特徴です。

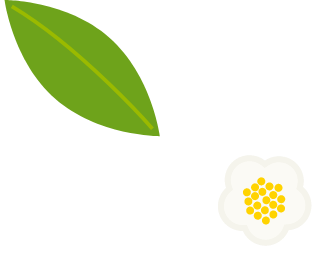


いわた茶の歴史
磐田市で茶の栽培が始まったのは、今から約百年以上前の明治初期に遡ります。戦後ヤブキタの普及と共に面積は拡大し、昭和33年の磐田原簡易水道の完成、昭和43年より県営磐田原圃場整備事業が実施されると畑地灌漑設備も整い、磐田市茶行の様相は一変してきたようです。

近代日本の造船技術の先駆者で、明治初期に磐田原台地に茶園を開拓した海軍中将男爵赤松則良の邸宅跡です。
明治20年代に建てられた門・堀・土蔵は県・市の指定文化財となっています。敷地内には庭園と旧赤松記念館があり、記念館では旧赤松家ゆかりの文化財や寄贈資料等を展示しています。